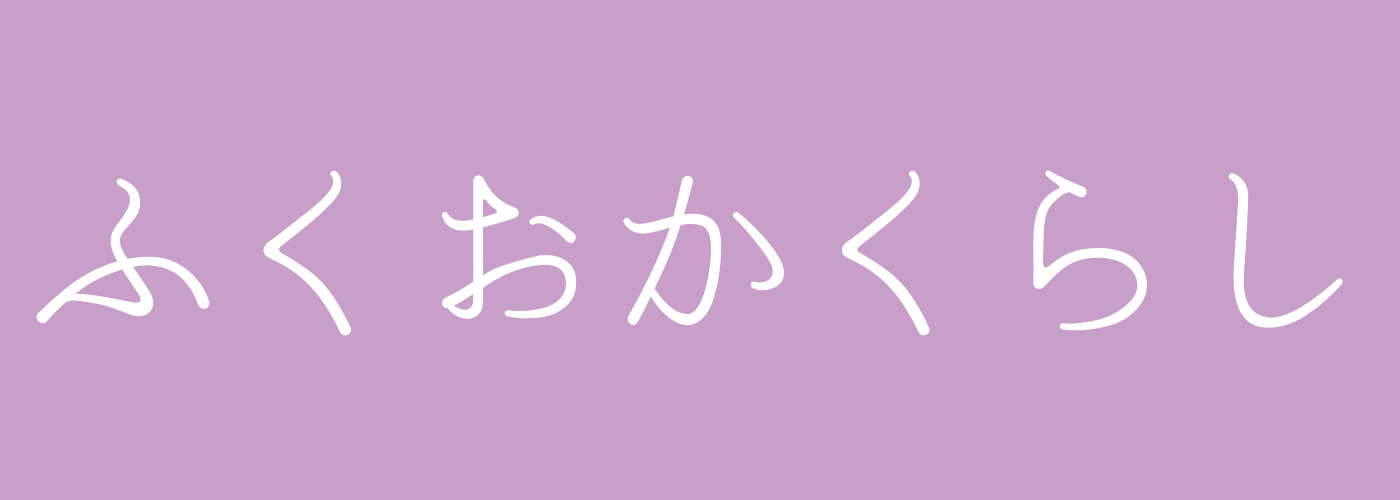この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
以前から気になっていた一冊を、ようやく手に取った。
『たゆたえども沈まず』
この一冊の物語を読み終えた今、セーヌ川に浮かんだ小舟がゆらゆらと揺れ、上下する様が目に浮かぶ。
たゆたえども沈まなかったのは、異国の地で自国の”美”を広め続けた日本人か、それとも、新しい美しさを表現しようとしてもがき続けた芸術家か。芸術家である兄を一心に支え続けた、一人の青年か―。
本小説は、パリにて日本美術を広めた美術商・林忠正と日本人青年の加納重吉・今や世界的な画家であるゴッホと、その弟テオを中心として展開していく。
舞台は時代の転換期、1800年代後半のフランス・パリだ。
人々は鎖国から開放された新しい国・ジャポンの文化と芸術に魅了され、心を奪われ、揺り動かされていく。
ジャポニズム真っ只中のフランス。開国後、西欧に文化に惹かれ、変化してゆく日本。
それぞれの国が異なる文化に惹きつけられる中で。時代は進む。
ゴッホと聞けば、誰しも抱くイメージがあるだろう。
『ひまわり』『星月夜』。あるいは、耳を切り落とした狂気の画家―。
しかし、本当の彼の生涯は、いかなるものであったのだろうか。
彼がアルルに移ってからの生活は、弟テオに宛てた手紙により伺い知ることができるが、パリ時代の生活は詳細な記録がなく、はっきりとは分かっていない。
だが本作を読んだ後には、「ゴッホとテオは林や加納と交流し、苦悩し、日本の美に感動し、日々作品を生み出し続けた。そんな過去がきっと存在した」と、信じたくなってしまう。
加納を中心とした繊細な人物描写に、目の前のモノクロの景色が一気に色づいていくような感覚を覚えた。
今や世界中で愛される偉大な画家の生涯は、重く暗く、苦しみに満ちたものであった。
しかしその数々の苦悩が、彼の作品から感じられる鼓動やうねりだと考えると、合点がいく。
今までゴッホの絵を観る度に感じてきた表現しきれぬ力について、少し理解できたように感じた。
たゆたえども、沈まず。ゴッホの乗った小舟は、幾度の波に耐えきれず、転覆してしまったかもしれない。
けれど、彼が生み出した作品は、世界の宝として人々に愛され、受け継がれている。
日本人美術商と、一人のオランダ人画家の運命は、史実では交わることはなかったであろうが、この物語には描かれていない四人の交流を夢見ずにはいられない。
多くの人が持っている、「情熱と狂気の画家」としてのゴッホイメージを崩したい。
そんな想いが、この一冊には詰まっていると感じる。